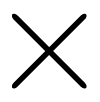notes
*
20180109

雪の記憶。
時々、雪の降る街に、また住みたいと思う。
雪があたり一面を白に染めていく風景を思い浮かべると、懐かしい気持ちになる。
それは住んでいるこの街の陽気のせいなのか、もっと奥底の感覚なのか。
こどもの頃、わたしの暮らす街には、冬には冬らしい雪が降った。
朝、学校に行くときにはみえていた道が、夕方帰る頃には道がなくなるほどに一面雪におおわれて、膝くらいまでの雪をかき分けて家まで帰った日もあった。
夜中のあまりの静けさに、しんしんと、それこそほんとうに、無音のはずなのにしんしんという音がするような雪が中庭に降りつづいていて、街灯の明かりに染まる雪のかさなるすがたに目をうばわれ、眠れなくなったりもした。
圧倒的な白の世界。
音がないのに、音がするような、色がないのに、色があるような、雪の世界。
ことばはなく、ただ存在だけがあるような世界。
その白の雪の記憶が強くこころに残っていて、それはわたしの絶対的美意識のようなものをつくっていると思うところがある。
揺るがないいつもそこにある白い風景。すきな余白や余韻や空白はとても大事なものとして、その白の記憶につながる。
いつでもその世界にもどりたい気持ちになる。
大人になって、雪がほとんど降らない街に住んで、不意を突くように降る雪は、なんだか高揚するものとしてあらわれて、白の記憶とは別のものである。
あの静けさ。こころにも染まってゆく白。静けさが染みわたって外と内がつながるような感覚。
もう儚い記憶の遠い憧れのようなものなのかもしれない。
それでも、その白がふと、たしかに、自分を包んでくれるような気もしている。
また、雪の降る街に住みたいと思う。