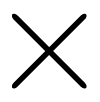notes
*
20180701

蝋燭を灯す。
朝のヨガと瞑想のとき、日中の食事のテーブルで、静寂とともに、音とともに。
明るい時間でも、灯りの気配はこころを落ち着かせ、ゆったりとしずかな時間をつくってくれる。
それでもやはり、日のひかりがゆっくりと落ちてゆく夕暮れの時間に蝋燭を灯すのは特別なひとときだ。
ひかりのなかにひっそりとあった炎が、次第に闇のなかにくっきりと存在してくる。
見えるものが消え、見えないものが見えてくるような時間。
ゆらぎと色の濃淡はほんとうにうつくしく、じっと見ていると呼吸が深くなり、こころがほどけていくような気がする。
そして、炎は遠いなつかしさを呼びおこす。
こころの奥底の、いまでない時間軸のなかに引きこまれるようで、ずっとずっとむかしもこんなふうに炎を見つめていたのだという記憶を灯してくれるようだ。
むかしもいまも炎の灯りはいつもしずかに、そばによりそって見守ってくれていたのだという親しさを感じる。
蝋燭を灯すようになったきっかけは、3.11のあとの計画停電から。
なんどもあったその時間をしのぐために、量販店でおおきな蝋燭を買って、夜暗くなるころに恐る恐る灯した時間。音を発する何もかもが停電で消えている空間は驚くほどしずかで、夜がすべてを吸いこんでしまうのではないかと感じるくらい闇の強さがあって、そのときは慣れない炎を、頼りにできるのかできないのかわからないような心許ない気持ちで見つめながら、闇と不安のなか隣にひっそりと灯りがあった。
日々のなか灯りをとりいれて、いまのわたしには、蝋燭の炎は親密でなくてはならないものとなっている。
ひかりをふくんだような白いうつくしい蝋燭は、炎の気配をまっすぐ純粋につたえてくれる。
灯りとともに、こころに静謐でゆたかな時間がおとずれる。震災のそのときの灯りのことを思い出すと、世界には今も不安のなかで蝋燭を灯しているひとがいるのだと思う。
蝋燭の灯りが、ささやかでもこころにあたたかさを灯すことを願う。