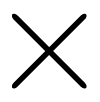notes
*
20200709

枝切りばさみでばちばちとヤマモモの枝を切ってゆくと、枝からふわっとヤマモモの実の甘い香りがした。
そうか、実は木の香りを携えて成るのだ、ということにはじめて気がつく。
よく考えればあたりまえなのだけれど、実際にその香りを体験してわかることだ。
紙を植物で染めるというのを試してみたくて、木を剪定して煮詰めて、染液を作ってみている。
先日はシャリンバイ、ヤマモモ、そして今日はロウバイの枝を細かく切って煮詰めはじめた。
調べてみると、身近にあるいろいろな木で染めることができることを知る。
モッコク、ツバキも染められそう。カラタネオガタマはどうだろう。そんな目で木を眺めてみるのも新鮮である。
シャリンバイからは桃色があらわれた。思いがけず華やかな色。咲く花はひっそりとした白なのだけど。
ヤマモモ染めの媚茶という色は「媚びるような色っぽい色」と江戸時代にとても流行った色だそうだ。
媚茶色の着物をまとう、町ゆく人を想像してみる。
化学染料ができるまでは、ずっと、植物の色を身につけて暮らしていたのだ。見た目のうつくしさや、布や身を守るものとして。
自分の側ににあるよく知った木で、剪定するついでの時に、枝をいただく。
本来ならば、花や実のなる前、芽吹きのエネルギーを蓄えている時期が一番濃く色がでるのだろうと思うけれど、それらもすぎて枝が生い茂った頃に「すこしいもらいます。」という気持ちで剪定して枝をはらう。
あまり欲張らず、木にも、自分の気持ちにも、無理のない量で。
紙に染液を刷毛でのせていく。水をふくんだ水彩絵の具のように淡い色が広がる。
洋紙と和紙とでも感じが変わる。コットンを多く含む洋紙にはしっかりと色があらわれる。
手をかけた、ということがあるのかもしれないけれど、植物の色をのせることで、紙がより親密に感じられる。
色をまとうことで、紙そのものが息をはじめるような気もする。あたらしい紙が生まれる。
(写真はシャリンバイの色のあらわれ。内に秘めた色。)