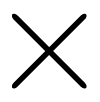notes
*
20210315

ここ数日、手作業の時間に、修道院のドキュメンタリー映画を流している。フランス、アルプス山脈に建つグランド・シャルトルーズ修道院。
この修道院の様子を綴った映画は、ナレーションも音楽もなく、照明を使用しないでただ1台のカメラで撮られている。
聴こえてくるのは、鐘の音、そして、祈り。あとは、静かな生活の音と季節の風景の音のみ。
作業の手を止めて画面に目を向けると、白い服を着た修道士の祈りの姿がある。
<大いなる沈黙へーグランド・シャルトルーズ修道院>この映画を初めて観たのは何年前だったか。
映画のポスターが雪につつまれた修道院の風景で、そんな冬のつめたさも記憶のはるか遠くにあるような7月夏のはじめだった。
岩波ホールに入ると列がかなり伸びていて、思いのほかたくさんのひとが来ている。よく見ると年配の方も多い。
そうか、普段から教会に行くひと達がたくさん、この映画を観るために来ているのだとその時気がついた。
暗闇の映画館のスクリーンに、アルプスの移り変わる季節の風景とともに、淡々と、グランド・シャルトルーズ修道院の祈りの日々が映し出される。
この場所だけにある深遠な時間軸、静謐で厳かな時間。緻密で精誠な空気。簡素でありながらもなぜかとても豊かに思える修道士の姿。
そこに流れる時間は、普段のわたしのいる世界とは全く異なる時間であった。
修道士の暮らしは厳かな祈りが日々のほぼ中心であるが、それぞれの作業もあり、薪を切り出す、食事を作る、服を作る、庭をととのえる、製本をする、髪を切るなど、どんな時もひとり静かに淡々と作業が行われている。(修道院には欠かせない猫にご飯を届けるというのもその中に。猫はネズミ退治のために大切にされているのだ)
食事の時間もひとり。食事を終えたスプーンを少しの水で丁寧に洗う、布で拭う。水もスプーンも布も、行為も、すべて大切にあつかわれている。
皆での祈りの時間以外、ほとんどの時間を、ひとり、神に仕えてすごす。
誰かが褒めてくれるわけではない。それでも、神がみていてくれる。
神がいつも側にいるという、その日々のこころの有り様とはどんなだろうか。
「肉体への執着を手放すと、生死のサイクルから解放される。」という言葉を聞いたことがあるけれど、修道士の姿を観ていてその言葉を思い出した。
いつの時も変わらず、あの場所があり、彼らは祈っているのだ。ずっとむかしも、そして、たった今の今も。
あの修道院の時間軸を思いながら映画館を後にした。
「祈り」と「献身」という言葉をこころに思うと、とても静かな気持ちになる。
自分の日々の行為のなかに、そんな慎ましやかなこころが一滴でも注がれればと切に願う。
お茶を煎れる時、お皿を拭く時、庭の花を花瓶にいける時、暮らしのなかで細部にその一滴が宿るようにあれたらと思う。
フランスの修道院ですごす修道士(フランソワという名だった)の姿を思い出すと、なぜかこちら側にいるわたしの、ひとりという時間も、静かでおだやかな気持ちが湧いてくる。
耳に届くまわりの音が雑音でなく、彩りをもって、いつもと違う音に聞こえる。
もちろん祈りと献身という言葉をあつかっても、修道士とわたしとでは、地球と砂粒ほどのおおきさの相違はあるけれど。修道士のつよい確信もふくめて。(並べ比べてみるのもおかしな話だけれども)
それでも、誰かが褒めてくれることを求めるのでなく、自分の神がみていてくれる、という思い。ささやかでも、祈るように、というなかでの行為。
そんなことを思うと、自分のいるいまという世界が、静かにかわってゆくのがわかる。
映画の、グランド・シャルトルーズ修道院をつつむアルプスの四季の風景がとてもうつくしく、こころに余韻が映る。
(猫のすいとあるはシャルトリュー種。君たちは修道院と繋がっている?)